こんにちは、FPなおやんです。
法人のお客様で、 決算で黒字が出たんだけど、法人税の納付で現金が足りません。というお話がありました。
決算書で利益が出ているように見えても、その後の税金の支払いにより資金繰りが苦しくなるケースは少なくありません。
今回は、利益や現預金に直接影響する税金の仕組みについて簡単に説明していきます。
企業の経理担当者や法人営業を行っている方は正確に把握できるように理解しましょう。
この記事でわかること
- 決算書における法人税・消費税の表示方法
- 納付による現預金の変化
1. 決算書における法人税の表示方法
まずは法人税について説明していきます。
法人税は会社が1年間の利益に対して納める税金で、決算書上は以下のように扱われます。
(1) 損益計算書(P/L)
損益計算書では、法人税は「法人税等」として当期利益を計算する際の費用として計上されます。
営業利益:500万円
法人税等:100万円
当期利益:400万円
損益計算書では、法人税等という形で表示されます。
(2) 貸借対照表(B/S)
次に、貸借対照表を見ていきましょう。
決算時点でまだ法人税を納付していない場合、負債の部に「未払法人税」として計上されます。
納付前の時点では現金は減っていませんが、将来的に支払う義務がある金額として負債に載せる必要があります。
法人税等 100万円 / 未払法人税 100万円
これが現金で納付後には、未払法人税がなくなり、現金が減少します。
未払法人税 100万円 / 現金 100万円
2. 決算書における消費税の表示方法
続いて、決算書における消費税の表示方法について解説していきます。
消費税は事業者が商品やサービスを提供する際に預かる税金ですが、会社の収益ではありません。
そのため、決算書上では費用として計上せず、預かり金・未払金として扱うのが基本です。
(1) 貸借対照表(B/S)
決算時点でまだ消費税を納付していない場合、負債の部に「未払消費税」として計上されます。
未払消費税 30万円
この時点では、現金はまだ減りません。
(2) 納付後の処理
実際に現金で納付した場合、未払消費税が消え、現金が減少します。
未払消費税 30万円 / 現金 30万円
3. 決算後2か月以内の納付と現預金の関係
法人税・消費税は、通常決算日から2か月以内に納付することが法律で定められています(中間申告や特例を除く)。
このタイミングは会社の資金繰りに大きな影響を与えます。
(1) 未払計上時点
決算書上では、法人税や消費税は負債として計上されている(まだ払っていない)ため、現金残高には影響しません。
経営者は帳簿上の利益を確認できますが、まだ現金が減っていないことに注意が必要です。
(2) 納付時点
2か月以内に実際に税金を支払うと、負債が減り、現金も減少します。
たとえば決算時に未払法人税100万円、未払消費税30万円がある場合、納付後には合計130万円の現金が減ります。
- 資金繰りに注意が必要
- 現金が十分にないと納税が資金的に厳しくなる
- 法人税と消費税の合計額が現金残高とほぼ同じ場合は、納付のタイミングで資金繰りが一時的に逼迫する可能性があります。
4. 経営者が知っておくべきポイント
以上を踏まえ、経営者や経理担当者が知っておくべきポイントをまとめます。
- 損益計算書に表示される法人税は費用
- 消費税は先に預り、後で払うお金なので、費用ではない
- これから納付すべき金額は、貸借対照表の未払税金として計上される
- 法人税と消費税は2か月以内に納付する
- 決算書は納税前で、税金納付により、これから現金が減る
- 納付スケジュールと現金残高の管理が重要
5. まとめ
これまでの内容をまとめていきます。
法人税と消費税は決算書上で異なる扱いを受けます。
| 損益計算書 | 貸借対照表 | |
| 法人税 | 費用 | 未払法人税 |
| 消費税 | - | 未払消費税 |
決算後2か月以内に納付することで、現金が減少します。
- 利益が出ている場合でも資金繰りに注意が必要
- 決算書を見ながら利益だけでなく現金の動きも把握する
決算書は「利益の成績表」であると同時に「資金繰りの地図」です。
納税は最悪の場合、黒字倒産につながるリスクもあります。
納税の仕組みやタイミングをしっかりと理解し、健全な経営判断を行っていきましょう!

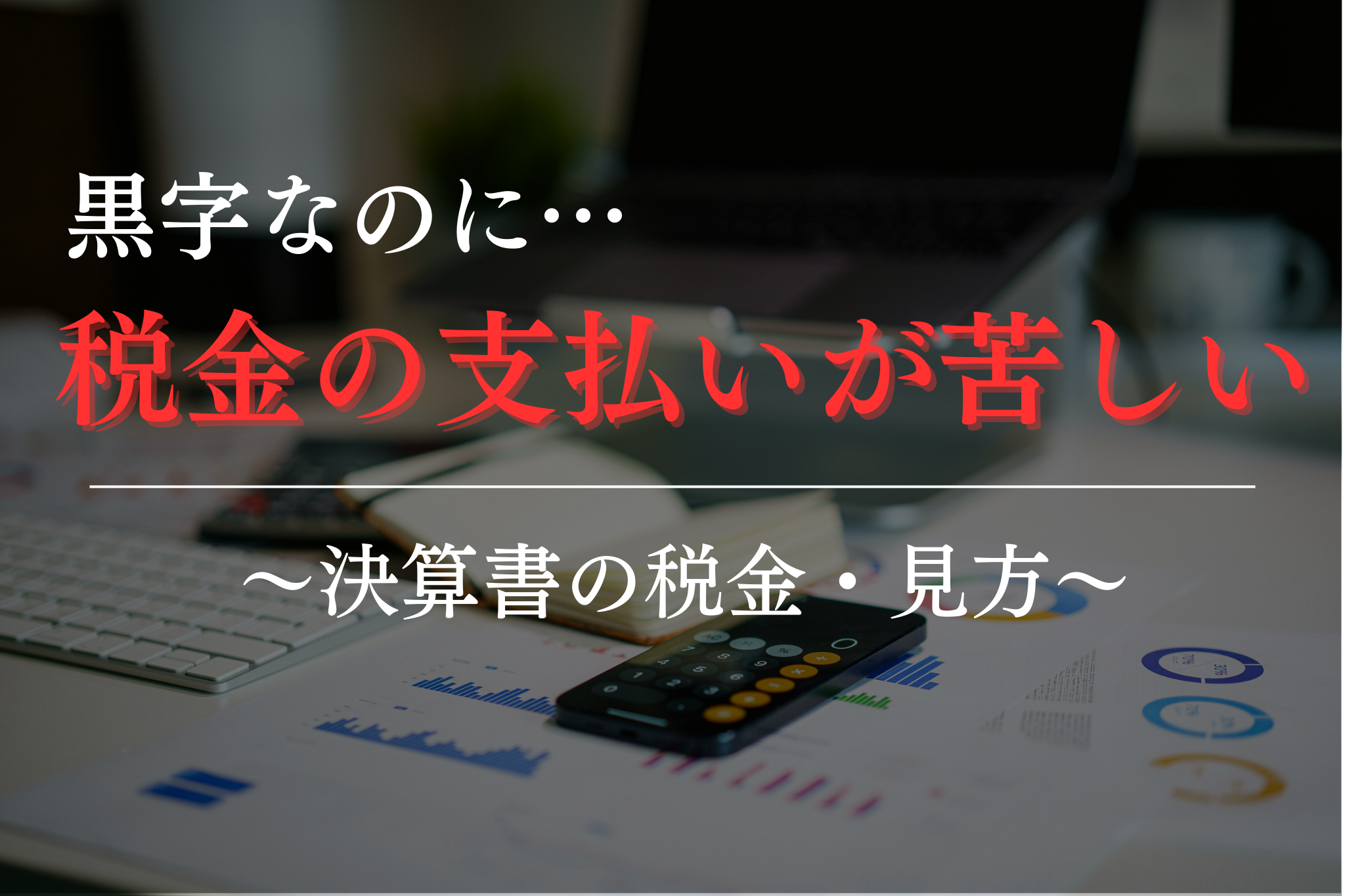
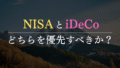
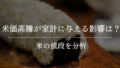
コメント